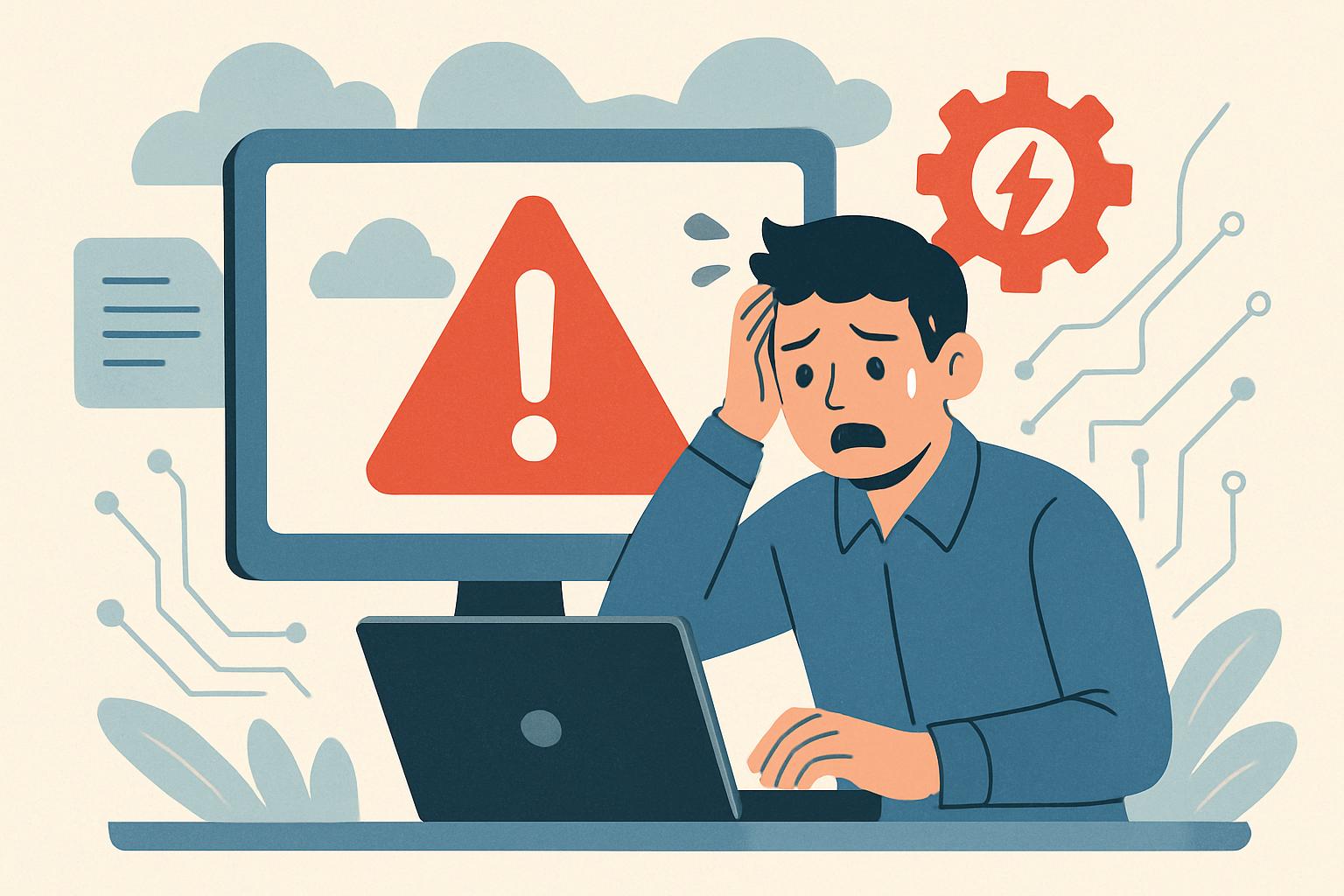突然のシステム障害やサービス停止といった「インシデント」が発生し、その対応に追われていませんか?インシデント管理とは、単なる場当たり的な障害対応ではなく、ビジネスへの影響を最小限に抑え、迅速にサービスを復旧させるための体系的なプロセスです。本記事では、インシデント管理の基本からITILに準拠した具体的なプロセスフロー、効果的な体制構築のポイントまでを網羅的に解説します。効果的なインシデント管理の導入は、迅速な復旧だけでなく、ナレッジの蓄積による再発防止とサービス品質の向上に不可欠です。おすすめのツールや国内企業の成功事例も交え、属人化を防ぎ安定したシステム運用を実現する具体的な方法を明らかにします。
インシデント管理とは何か その目的と重要性を解説
現代のビジネスにおいて、ITシステムの安定稼働は事業継続の生命線です。しかし、どれだけ万全な対策を講じても、システム障害やサービスの品質低下といった「インシデント」を完全にゼロにすることは困難です。そこで重要になるのが「インシデント管理」です。インシデント管理は、予期せぬトラブルが発生した際に、その影響を最小限に抑え、迅速にサービスを正常な状態へ復旧させるための体系的なアプローチを指します。本章では、インシデント管理の基本的な定義から、その目的、そしてビジネスにおける重要性について詳しく解説します。
インシデント管理の基本的な定義
インシデント管理を理解するために、まず「インシデント」という言葉の定義から確認しましょう。ITサービスマネジメントのベストプラクティス集であるITIL(Information Technology Infrastructure Library)では、インシデントを「ITサービスの中断、またはITサービスの品質を低下させる可能性のある、計画外の出来事」と定義しています。具体的には、以下のような事象がインシデントに該当します。
- Webサイトにアクセスできない
- アプリケーションの動作が極端に遅い
- サーバーがダウンした
- ネットワークに接続できない
- プリンターから印刷ができない
そして「インシデント管理」とは、これらのインシデントが発生してから、サービスを正常な状態に復旧させるまでの一連のプロセス全体を指します。その最大の目的は、あくまでも「迅速なサービス復旧」にあり、ビジネスへの影響を最小限に食い止めることです。根本的な原因を追究するよりも、まずは応急処置を施してサービスを元に戻すことが最優先されます。
インシデント管理がビジネスにもたらすメリット
適切なインシデント管理体制を構築することは、企業に多くのメリットをもたらします。単なる障害対応にとどまらず、ビジネスの成長と安定に直結する重要な活動です。
- サービス品質の向上と顧客満足度の維持
- インシデントに迅速かつ的確に対応することで、サービス停止時間を短縮し、顧客や利用者の不満を最小限に抑えることができます。これは、顧客満足度の維持・向上に直接つながり、企業の信頼性を高めます。
- ビジネス機会損失の最小化
- ECサイトの停止は売上の損失に、社内システムの停止は業務の停滞に直結します。インシデント管理は、システムのダウンタイムを最小化することで、売上や生産性への悪影響を防ぎます。
- 対応プロセスの標準化と属人化の防止
- インシデントの記録、担当者の割り当て、対応手順などを標準化することで、担当者のスキルや経験に依存しない、一貫性のある高品質な対応が可能になります。これにより、俗に言う「あの人でなければ対応できない」といった属人化を防ぎます。
- ナレッジの蓄積と将来への活用
- 発生したインシデントの内容や対応履歴を記録・蓄積することは、組織にとって貴重な資産となります。過去の事例を分析することで、将来発生する同様のインシデントに対して、より迅速で効果的な対応が可能になります。
問題管理や変更管理との違い
インシデント管理は、「問題管理」や「変更管理」といった他のITサービスマネジメントプロセスと混同されがちです。それぞれの目的と役割は明確に異なり、これらを正しく理解することが効果的な運用には不可欠です。以下の表でそれぞれの違いを整理しました。
| 管理プロセス | 目的 | 主な活動内容 | 例えるなら |
|---|---|---|---|
| インシデント管理 | サービスの迅速な復旧(応急処置)とビジネス影響の最小化 | インシデントの検知、記録、分類、優先順位付け、診断、解決、クローズ | 火事を素早く消し止める消防士 |
| 問題管理 | インシデントの根本原因の特定と恒久的な解決策の策定(再発防止) | 根本原因分析(RCA)、既知のエラーの記録、恒久的な解決策の提案 | 出火原因を調査する火災調査官 |
| 変更管理 | ITインフラへの変更に伴うリスクを管理し、変更に起因するインシデントを未然に防ぐ | 変更要求の評価、計画、承認、実装、レビュー | 火事が起きにくい建物を設計・施工管理する建築士 |
このように、インシデント管理が「今起きている火事を消す」活動であるのに対し、問題管理は「なぜ火事が起きたのかを調査し、二度と起きないようにする」活動です。そして変更管理は、「そもそも火事が起きないように、安全に変更作業を進める」ための活動と言えます。これらは独立しているのではなく、相互に連携することで、ITサービスの安定性をより強固なものにしていきます。
ITILに学ぶインシデント管理の基本プロセスフロー
インシデント管理を体系的かつ効率的に進めるためには、世界的なITサービスマネジメントの成功事例をまとめたフレームワークである「ITIL(Information Technology Infrastructure Library)」に基づいたプロセスフローを理解することが不可欠です。ITILでは、インシデントの発生から解決、そして終結までの一連の流れを標準化しており、多くの企業で採用されています。ここでは、ITILに準拠した基本的な6つのステップを具体的に解説します。
ステップ1 インシデントの検知と記録
インシデント管理の最初のステップは、インシデントの発生を「検知」し、その内容を正確に「記録」することです。検知のきっかけは、ユーザーからの電話やメール、チャットによる問い合わせ、あるいは監視ツールが発するアラートなど多岐にわたります。どのような経路であっても、すべてのインシデントを例外なく管理システムに記録することが、対応漏れを防ぎ、後々の分析に役立てるための第一歩となります。
記録する際には、以下の情報を網羅的に入力することが重要です。
- インシデントの一意な識別番号(ID)
- 報告者の氏名・部署・連絡先
- インシデントの発生日時
- 利用しているサービスや機器の名称
- 発生している事象の具体的な内容(エラーメッセージなど)
- インシデントの受付担当者
これらの情報を正確に記録することで、担当者が変わってもスムーズな引き継ぎが可能になります。
ステップ2 インシデントの分類と優先度付け
記録されたインシデントは、次に「分類」と「優先度付け」を行います。これは、適切な担当チームへ迅速に割り振り、対応すべきインシデントの順序を決定するための重要なプロセスです。
分類では、「ネットワーク障害」「サーバー障害」「アプリケーションのバグ」といったカテゴリに分けます。これにより、専門知識を持つ適切な担当者へスムーズに割り当てることができます。
優先度付けは、ビジネスへの影響を最小限に抑えるために不可欠です。一般的には、事業への影響範囲を示す「影響度」と、対応を迫られる緊急性を示す「緊急度」の2つの軸を組み合わせたマトリクスで決定します。この優先度付けによって、限られたリソースを最も重要なインシデントに集中させることができます。
| 影響度:大(基幹システム停止など) | 影響度:中(一部門の業務停止など) | 影響度:小(個人PCの不具合など) | |
|---|---|---|---|
| 緊急度:高 | 最優先(1) | 高(2) | 中(3) |
| 緊急度:中 | 高(2) | 中(3) | 低(4) |
| 緊急度:低 | 中(3) | 低(4) | 低(4) |
ステップ3 初期調査と診断
優先度付けが完了したら、一次対応担当者(多くはサービスデスクやヘルプデスク)が初期調査と診断を行います。この段階の目的は、過去の類似インシデントやナレッジベースを参照し、既知の解決策で迅速に対応することです。
担当者は、ユーザーにヒアリングを行いながら状況を正確に把握し、ナレッジベースに蓄積されたFAQや対応手順書を確認します。もし過去に同様の事象があれば、その手順に従って対応を進めます。このステップで解決できれば、最も迅速かつ効率的にサービスを復旧させることが可能です。
ステップ4 エスカレーション
初期調査で解決策が見つからない場合や、より専門的な知識・権限が必要な場合は、インシデントを上位の専門チームへ「エスカレーション(引き継ぎ)」します。エスカレーションは、インシデントが解決されないまま滞留することを防ぎ、SLA(サービスレベル合意書)で定められた時間内に解決するための重要なプロセスです。
エスカレーションには、より専門的な技術を持つチームへ引き継ぐ「機能的エスカレーション」と、インシデントの重要度に応じて上位の管理者へ報告・判断を仰ぐ「階層的エスカレーション」の2種類があります。引き継ぎの際は、これまでの対応履歴や調査内容を正確に伝えることが、その後のスムーズな対応に繋がります。
ステップ5 解決と復旧
エスカレーションを受けた専門チームは、インシデントの根本原因を特定し、サービスを正常な状態に戻すための「解決」と「復旧」作業を実施します。原因究明のために、ログの解析やシステムの詳細な調査が行われます。
解決策には、恒久的な対策を施す場合と、まずはサービスを復旧させるための暫定的な回避策(ワークアラウンド)を講じる場合があります。いずれの場合も、対策を適用した後は、サービスが正常に稼働していることを十分にテスト・確認し、ユーザーに解決した旨を報告します。この報告をもって、ユーザーは業務を再開できます。
ステップ6 インシデントのクローズとナレッジ化
ユーザーがサービスの復旧を確認し、問題が解決したことに合意したら、インシデントを「クローズ(終結)」します。しかし、単にクローズして終わりではありません。今回のインシデント対応で得られた知見をナレッジとして蓄積し、組織全体の財産とすることが最も重要です。
具体的には、以下の情報を整理し、ナレッジベースに登録します。
- 発生した事象
- 根本原因
- 実施した具体的な解決策
- 対応にかかった時間
このようにナレッジを蓄積・共有する文化を醸成することで、将来同様のインシデントが発生した際に、誰もが迅速かつ的確に対応できるようになり、組織全体の対応力向上と業務の属人化解消に繋がります。
効果的なインシデント管理体制を構築する3つのポイント
インシデント管理のプロセスフローを理解しても、それを実行する「体制」が整っていなければ、絵に描いた餅になってしまいます。ツールを導入するだけでは不十分で、組織としてインシデントに対応するための基盤作りが不可欠です。ここでは、迅速かつ確実なインシデント対応を実現するために、特に重要となる3つのポイントを解説します。
役割と責任範囲を明確にする
インシデント発生時に最も避けたいのは、「誰が何をすべきか」が曖昧なために対応が遅れたり、担当者間で責任の押し付け合いが発生したりする事態です。こうした混乱を防ぎ、担当者個人のスキルに依存する属人化を解消するためには、役割と責任範囲の事前定義が極めて重要です。
具体的には、インシデントの受付と一次切り分けを行う「サービスデスク」、技術的な調査と復旧作業を行う「専門チーム(二次対応)」、対応全体の指揮を執る「インシデントマネージャー」といった役割を定めます。さらに、それぞれの役割が「何を」「どこまで」責任を持つのかを明確にするために、「RACIチャート」などのフレームワークを活用すると効果的です。
| アクティビティ | サービスデスク | 専門チーム | インシデントマネージャー | 経営層 |
|---|---|---|---|---|
| インシデントの記録 | R (実行責任者) | I (情報提供を受ける) | A (説明責任者) | I (情報提供を受ける) |
| 初期調査・一次対応 | R (実行責任者) | S (支援者) | A (説明責任者) | |
| 専門的な調査・復旧 | I (情報提供を受ける) | R (実行責任者) | A (説明責任者) | C (相談を受ける) |
| 関係者への進捗報告 | S (支援者) | I (情報提供を受ける) | R (実行責任者) | I (情報提供を受ける) |
| インシデントのクローズ | I (情報提供を受ける) | S (支援者) | R (実行責任者) |
R: Responsible (実行責任者), A: Accountable (説明責任者), C: Consulted (相談先), I: Informed (報告先), S: Supporter (支援者)
このように役割と責任を可視化することで、インシデント発生時に各担当者が迷うことなく、自身のタスクに集中できるようになります。
コミュニケーションルールを策定する
インシデント対応において、迅速な情報共有は成功の鍵を握ります。報告の遅れや内容の齟齬は、誤った判断や対応の重複を招き、解決までの時間を長引かせる原因となります。「誰が、いつ、誰に、何を、どのように」伝えるかを定めた明確なコミュニケーションルールを策定し、関係者全員で徹底することが重要です。
策定すべきルールのポイントは以下の通りです。
- 報告ルートの確立: インシデントの重要度や緊急度に応じて、報告すべき相手(上長、関係部署、経営層など)とエスカレーションの基準を明確にします。
- 連絡手段の統一: 緊急連絡は電話、記録を残すべきやり取りはビジネスチャット(Microsoft TeamsやSlackなど)、顧客への公式な報告はメールなど、状況に応じた連絡手段を事前に定めておきます。
- 報告フォーマットの標準化: 報告内容の抜け漏れを防ぎ、情報を正確に伝えるために、報告用のテンプレートを用意します。5W1Hを意識したフォーマットが有効です。
| 項目 | |
|---|---|
| 発生日時 (When) | YYYY年MM月DD日 HH:MM頃 |
| 発生場所 (Where) | ○○サーバー、△△システム |
| 影響範囲 (Who/What) | ○○部の業務、Webサイトの閲覧 |
| 事象 (What) | (例:Webサイトにアクセスすると503エラーが表示される) |
| 原因(仮説) (Why) | (例:昨夜のシステムメンテナンスに起因する可能性) |
| 現在の対応状況 (How) | (例:サーバーのログを確認中) |
こうしたルールを整備することで、冷静な判断が難しい緊急時でも、組織として一貫性のあるスムーズなコミュニケーションが実現できます。
ナレッジベースを整備し活用する文化を醸成する
インシデントは、一度解決すれば終わりではありません。対応の過程で得られた知見や手順を組織の資産として蓄積し、次に活かす仕組みが不可欠です。過去のインシデント対応記録を「ナレッジ」として整備し、誰もが参照・活用できる文化を醸成することで、組織全体の対応能力は飛躍的に向上します。
ナレッジベースの整備と活用には、以下の取り組みが効果的です。
- 対応記録のテンプレート化: インシデントをクローズする際に、必ず「発生事象」「原因」「暫定対応」「恒久対策」などの項目を記録する運用を徹底します。これにより、質の高いナレッジが蓄積されやすくなります。
- 検索性の高いツールの導入: 必要な情報へ迅速にたどり着けるよう、タグ付け機能や全文検索機能が充実したナレッジベースツール(ConfluenceやNotionなど)を導入します。FAQや手順書として整理することも有効です。
- ナレッジ活用を評価する文化づくり: 新たなインシデント対応に着手する際は、まずナレッジベースを検索することをチームのルールとします。また、有益なナレッジを登録・更新した担当者を評価する仕組みを取り入れることで、ナレッジ蓄積へのモチベーションを高め、属人化の解消と継続的な業務改善を促進します。
ナレッジベースは、単なる記録保管庫ではありません。未来のインシデントを未然に防ぎ、発生してしまった場合でも迅速に解決するための「組織の集合知」として機能させる意識が、安定したシステム運用に繋がります。
インシデント管理を効率化するおすすめツール
インシデント管理をExcelやスプレッドシートで手作業で行っていると、対応漏れや情報共有の遅れ、担当者の引き継ぎが困難になるなど、多くの課題が発生します。これらの課題を解決し、迅速かつ体系的なインシデント管理を実現するためには、専用ツールの活用が不可欠です。ここでは、インシデント管理ツールの主な機能から、自社に最適なツールを選ぶための比較ポイント、そして国内で人気のツールまでを詳しくご紹介します。
インシデント管理ツールの主な機能
インシデント管理ツールには、障害対応を効率化し、サービス品質を向上させるための多彩な機能が搭載されています。代表的な機能を以下の表にまとめました。
| 機能名 | 概要 |
|---|---|
| チケット管理機能 | インシデントの発生からクローズまでを一元管理します。発生日時、担当者、対応状況、優先度などの情報を記録し、対応漏れを防ぎます。 |
| SLA管理機能 | サービスレベルアグリーメント(SLA)に基づき、対応期限を設定・監視します。期限が近づくとアラートで通知し、SLA遵守を支援します。 |
| ナレッジベース構築機能 | 過去のインシデント対応履歴や解決策をデータベース化します。FAQやマニュアルとして共有することで、対応の迅速化と属人化の解消に繋がります。 |
| 自動化・ワークフロー機能 | インシデントの優先度に応じた担当者の自動割り当てや、定型的な報告作業の自動化など、ワークフローを定義して手作業を削減します。 |
| レポート・分析機能 | インシデントの発生件数や解決時間、原因などを分析し、グラフやレポートとして可視化します。サービス品質の改善や再発防止策の立案に役立ちます。 |
ツール選定で失敗しないための比較ポイント
多種多様なインシデント管理ツールの中から、自社の課題や運用体制に最適なものを選ぶことが成功の鍵です。ツール選定で後悔しないために、特に重視すべき3つの比較ポイントを解説します。
ポイント1 操作性とカスタマイズ性
インシデント管理ツールは、IT部門の担当者だけでなく、状況によっては様々な部署の従業員が利用する可能性があります。誰にとっても直感的で分かりやすいインターフェースであるかは、ツールが組織に定着するための非常に重要な要素です。また、企業の運用フローはそれぞれ異なります。自社のワークフローに合わせて、入力項目やステータス、通知ルールなどを柔軟にカスタマイズできるかどうかも必ず確認しましょう。多くのツールで無料トライアルが提供されているため、実際に操作感を試してみることを強く推奨します。
ポイント2 外部ツールとの連携機能
インシデント管理は、単体で完結する業務ではありません。すでに社内で利用しているチャットツールや監視ツール、プロジェクト管理ツールなどとスムーズに連携できるかは、業務効率を大きく左右します。例えば、監視ツールが異常を検知した際に自動でインシデントを起票したり、チャットツールに対応状況を自動で通知したりする機能があれば、担当者の負担を大幅に軽減できます。API連携の可否や、連携可能なツールの種類を事前に確認することが重要です。
ポイント3 サポート体制の充実度
特に初めてインシデント管理ツールを導入する場合、設定方法や運用について不明点が出てくることは少なくありません。導入時の支援や、トラブル発生時に迅速に対応してくれる手厚いサポート体制があるかは、安心してツールを運用するための生命線です。日本語での問い合わせが可能か、対応時間は自社の業務時間に合っているか、サポート形式(電話、メール、チャットなど)は何か、といった点を事前にチェックしておきましょう。国産ツールや国内に拠点を持つベンダーは、手厚い日本語サポートを強みとしている場合が多いです。
国内で人気のインシデント管理ツール紹介
ここでは、日本国内で多くの企業に導入され、高い評価を得ている代表的なインシデント管理ツールをいくつかご紹介します。それぞれの特徴を比較し、自社の目的や規模に合ったツールを見つけてください。
| ツール名 | 主な特徴 | 向いている企業規模 |
|---|---|---|
| ServiceNow | ITILに完全準拠したITサービスマネジメント(ITSM)の代表格。インシデント管理だけでなく、問題管理、変更管理など幅広いプロセスを網羅。拡張性が高く、大規模な組織の複雑な要件にも対応可能。 | 中規模〜大企業 |
| Jira Service Management | 開発ツール「Jira」との連携が強力で、開発チームとサービスデスクの連携をスムーズにする。アジャイル開発との親和性が高く、DevOpsを推進する企業に最適。 | 小規模〜大企業 |
| Backlog | 国産のプロジェクト管理ツールだが、課題管理機能がインシデント管理にも活用可能。シンプルで直感的な操作性が特徴で、非エンジニアでも使いやすい。コストパフォーマンスに優れる。 | 小規模〜中規模 |
| PagerDuty | インシデント対応の自動化やオンコール(緊急呼び出し)管理に特化。多数の監視ツールと連携し、アラートを集約して適切な担当者に迅速に通知する機能が強力。 | 小規模〜大企業 |
| LMIS | 純国産のITIL準拠ITサービス管理ツール。日本の商習慣に合わせた機能や、手厚い日本語の導入・運用サポートが魅力。オンプレミス版とクラウド版から選択可能。 | 中規模〜大企業 |
ここで紹介した以外にも、多くの優れたツールが存在します。最も重要なのは、自社の課題を明確にし、その解決に最も貢献してくれるツールはどれかという視点で比較検討することです。各ツールのウェブサイトで詳細な機能を確認したり、無料トライアルを活用したりして、じっくりと選定を進めていきましょう。
インシデント管理の導入事例から学ぶ成功の秘訣
インシデント管理の理論やプロセスを理解しても、自社でどのように導入し、成果に繋げればよいかイメージが湧きにくいかもしれません。ここでは、インシデント管理を導入し、具体的な成果を上げた国内企業の事例を2つご紹介します。自社の課題と照らし合わせながら、成功の秘訣を探っていきましょう。
A社の事例 属人化を解消し対応時間を半減
中堅SaaS企業であるA社では、顧客からの問い合わせやシステム障害の対応が特定の担当者に依存し、属人化していることが長年の課題でした。担当者不在時には対応が大幅に遅延し、顧客満足度の低下を招いていました。
そこでA社は、インシデント管理ツールの導入とプロセスの標準化に着手。すべてのインシデント情報をツールに集約し、対応履歴やナレッジをリアルタイムで共有できる体制を構築しました。これにより、誰が対応しても一定の品質を保てるようになり、情報共有も円滑になりました。
| 項目 | 導入前 (Before) | 導入後 (After) |
|---|---|---|
| インシデント対応の状況 | 担当者しか状況を把握できず、対応がブラックボックス化。 | 対応状況がリアルタイムで可視化され、チーム全体でフォロー可能に。 |
| 平均対応時間 | 約4時間 | 約2時間(50%削減) |
| ナレッジの共有 | 個人の経験や記憶に依存。新人教育にも時間がかかっていた。 | ツール上でナレッジベースが構築され、類似インシデントへの対応が迅速化。 |
| 顧客満足度 | 対応遅延によるクレームが散見された。 | 迅速かつ的確な対応により、顧客満足度が向上。 |
A社の成功の秘訣は、単にツールを導入しただけではありません。「インシデントは必ずツールに記録する」「解決策は必ずナレッジとして登録する」といった運用ルールをチーム全体で徹底し、ナレッジを活用する文化を醸成したことが、属人化の解消と劇的な時間短縮に繋がったのです。
B社の事例 再発防止策の徹底でシステム安定稼働を実現
大手ECサイトを運営するB社では、サービスの急成長に伴いシステムが複雑化し、同じ原因による障害が繰り返し発生していました。インシデント発生時には迅速な復旧を最優先するあまり、根本原因の特定と再発防止策の実施が後手に回っていたのです。
この状況を打開するため、B社はITILに準拠した本格的なインシデント管理と問題管理のプロセスを導入。インシデント対応後、必ず根本原因分析(RCA: Root Cause Analysis)を行い、恒久的な解決策を策定する「問題管理」のフローを確立しました。これにより、場当たり的な対応から脱却し、システムの安定性を大幅に向上させることに成功しました。
| 項目 | 導入前 (Before) | 導入後 (After) |
|---|---|---|
| インシデントへの対応 | 暫定的な対応(ワークアラウンド)が中心で、同種の障害が頻発。 | 根本原因を特定し、恒久的な対策を実施するプロセスを確立。 |
| 同種インシデントの再発率 | 高い水準で推移。 | 80%削減に成功。 |
| システムの可用性 | 計画外のサービス停止がビジネスに影響を与えていた。 | システムの安定性が向上し、可用性SLA(サービス品質保証)の目標値を達成。 |
| 開発チームとの連携 | 障害対応の情報が十分に共有されていなかった。 | 問題管理を通じて得られた知見が開発チームにフィードバックされ、品質向上に貢献。 |
B社の成功要因は、インシデント管理を「その場しのぎの火消し」で終わらせず、再発防止を目的とする「問題管理」プロセスと密に連携させた点にあります。インシデントデータを分析し、システム全体の品質改善に繋げるという能動的なアプローチが、ビジネスの根幹であるシステムの安定稼働という大きな成果を生み出しました。
まとめ
本記事では、インシデント管理の定義や目的、ITILに準拠した具体的なプロセスフロー、そして効果的な体制を構築するためのポイントについて網羅的に解説しました。インシデント管理は、予期せぬシステム障害やサービス停止が発生した際に、ビジネスへの影響を最小限に抑え、迅速にサービスを復旧させるために不可欠な活動です。その成功は、場当たり的な対応ではなく、体系化されたプロセスを確実に実行できるかにかかっています。
効果的なインシデント管理を実現するためには、「役割と責任の明確化」「コミュニケーションルールの策定」「ナレッジベースの整備」という3つのポイントを押さえた体制構築が結論として重要になります。さらに、ServiceNowのようなITSMツールやBacklogのようなプロジェクト管理ツールを導入することで、対応の属人化を防ぎ、プロセス全体の効率を飛躍的に向上させることが可能です。
インシデントはいつ発生するか予測できません。しかし、適切な管理体制とプロセスがあれば、慌てることなく冷静に対処できます。この記事を参考に、自社のビジネスを守り、顧客からの信頼を高めるインシデント管理体制の構築をぜひ進めてください。
【PR】関連サイト
SHERPA SUITE
〒108-0073東京都港区三田1-2-22 東洋ビル
URL:https://www.sherpasuite.net/